多くの経営者や人事担当者が直面する、幹部や管理職が会社を辞めるという事態。しかし、一体彼らがなぜ辞めたくなるのか、その背景にはどのような理由があるのでしょうか。
その背景には、激務や強いストレス、部下の管理の難しさ、そして給与やキャリアの不安など、多岐にわたる理由が存在します。また、会社側の問題として挙げられるのは、コミュニケーション不足や不適切な評価制度です。
しかし、幸いなことに、これらの問題には解決策が存在します。ヒアリングや面談の実施、コミュニケーションの強化、そして労働環境の改善など、効果的な手段を通じて、管理職の満足度やモチベーションを高められるのです。
この記事では、管理職が退職を考える背後の理由や、そのような状況を生んでしまう会社の特徴、そして管理職の不満や悩みを解消するための具体的な対処法について深掘りしていきます。
中小企業の経営サポートを専門とし、クライアントとの経営会議を毎年500時間、累計3,000時間以上こなしてきた経営コーチ、EOS®(起業家のための経営システム)の専門家と一緒に考えていきましょう。
管理職を辞めたい理由とは

管理職の方々が辞めたいと感じる理由には様々なものがあります。
まずは、管理職が辞めたいと感じる9つの主要な理由を解説します。
理由(1)激務であること
管理職に就くと、その役割や業務内容が以前のものとは大きく異なることに多くの人が直面します。もちろん、部下として行っていた業務のフォローや監督はその主要な業務の一つとなりますが、それだけではありません。
管理職に昇進すると、多くのミーティングに参加する必要が出てきます。これは、部署の方針を決定するため、他部署との連携を図るため、あるいは上層部からの指示を受け取るためのものです。
これに加えて、各種の情報やデータの取りまとめを行う業務も増加します。部下の業績や進捗状況をまとめ、報告書として上層部への提出が求められることも少なくありません。
このような業務の増加は、当然、労働時間の伸びにつながります。終業時間を過ぎても終わらない業務、休日に持ち越されるミーティングや取りまとめ作業など、管理職としての責任とともに、激務の増加が一般的です。
そして、この激務は健康に対しても悪影響を及ぼすリスクがあります。長時間の労働は、疲労やストレスの蓄積を招き、これが体調不良や生活習慣病の原因となることが知られています。特に、継続的な過労は心身の健康を著しく害する可能性があるため、注意が必要です。
理由(2)仕事における強いストレス
管理職やリーダーの多い業務において、その中でも特に重要とされるのが部下の成果に対する責任です。部下が目標を達成することは、管理職の主要な役割の一つとなり、その結果は直接管理職の評価にも影響を与えることが多いです。
しかし、すべての部下が同じ能力や経験を持っているわけではないため、一人ひとりのニーズに合わせたサポートや指導が求められます。このような状況の中、期待される結果を出すための方針を考え、それを部下に伝え、実行させるプロセスは非常に複雑で、多くの時間やエネルギーを要します。
加えて、上司とのコミュニケーションも大きなストレスの原因となることがあります。管理職は、部下からの情報や要望を上層部に伝え、そのフィードバックや指示を部下に伝えるという役割を担います。
このコミュニケーションの中で、情報の伝達ミスや誤解が生じてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性もあるわけです。
また、複数のプロジェクトを同時進行で管理することも、管理職の大きな役割の一つです。それぞれのプロジェクトの進行状況を把握し、期限を守るための調整やスケジュールの変更が日常的に求められます。このような多岐にわたる業務の中で、適切な判断を下すための情報収集や分析、そしてそれを元にした決定は、ストレスを伴うことが少なくありません。
理由(3)部下の管理の難しさ
部下を持つリーダーや管理職の役割は、単に指示を出すだけではありません。部下それぞれが持つ独自の性格やスキル、さらには経験や背景といった多様な要素を考慮しながら、最も適切な方法での指導やフィードバックを行うことが求められます。この作業は、一見すると単純なもののように思えるかもしれませんが、実際には非常に複雑で繊細なものです。
例えば、ある部下は批判的なフィードバックを受けると、やる気を失うかもしれませんが、別の部下はそれを刺激として成長の機会と捉えるかもしれません。
同様に、一人の部下には具体的な指示が必要である一方で、別の部下には自ら考えて行動する自由が必要とされることもあります。これらの違いを見極め、それぞれの部下に合った指導方法を見つけ出すことは、時間と経験を要するものになるのです。
部下それぞれの違いを常に意識し、それに応じて柔軟に対応しなければならない状況は、リーダーや管理職にとって大きなプレッシャーとなり得ます。日々の業務の中で感じる難しさやプレッシャーは、自然なことであり、時には「この難しさから逃れたい」という気持ちが生まれることもあるでしょう。
部下の指導や育成は、長い時間をかけて築き上げる信頼関係の上に成り立っており、その過程の中で生じる様々な課題やストレスは、リーダーシップを担う者の持つ大きな挑戦の一つと言えるでしょう。
理由(4)給与の不足
仕事の中で、役職や職務内容によって負う責任の重さは異なります。特に管理職やリーダーのポジションに就くと、プロジェクトの成功や失敗、部下の成果やミス、業績の向上や低下など、多くの重要な事項に対しての責任が増していきます。
このような役職に就くと、その重責を背負うことになり、それに伴い日常の判断や行動には慎重さや緊張感が求められることが多くなります。
一般的には、そのような責任や役割の大きさに見合った報酬や待遇の提供が期待されます。しかし、実際には企業の経営状況や業界の標準、さらには企業文化や評価制度によって、高い責任に見合った報酬が得られるとは限りません。こうした状況下で、特に給与や待遇の上昇が限定的であると感じられる場合、自身が果たす役割とのバランスが取れていないという不満が生まれやすくなります。
例えば、あるプロジェクトが成功を収めた場合でも、それが給与やボーナスに直接反映されないことがあるかもしれません。また、日々の業務でのミスや過ちに対する責任は重くのしかかるものの、その努力や成果が給与に十分に反映されないこともあるでしょう。このような労力や責任の増加と報酬の不均衡が続くと、モチベーションの低下や仕事への熱意の喪失を引き起こす可能性があります。
特に、長期にわたってこのような状況が続くと、職場の離職率が上昇するリスクも高まります。従って、責任と報酬のバランスは、従業員の満足度や組織の健全性を保つ上で非常に重要な要素となるのです。
理由(5)キャリアに悩んでいる
働く上でのキャリアは、私たちの人生の中で非常に大きな部分を占めるものです。それ故、自分の仕事やキャリアに対しての期待や方向性、将来へのビジョンは非常に重要となります。しかし、時には自分が現在担当している仕事やポジションにおいて、将来の展望が明確に見えないことがあります。
例えば、自分の役職や業務内容が変わらないまま数年が経過する、進むべきキャリアの道筋がはっきりと描かれていない、などの状況が背景にあると考えられます。
また、仮に現在の業務が順調であっても、それが自分の中での長期的なキャリアゴールや目指すべき将来像と合致していないと感じる場合もあるかもしれません。例えば、自分が求めるスキルの習得や成長の機会が現在の職場やポジションでは限られている、自分の興味や情熱を持つ分野と現在の業務が異なる、などの理由が考えられます。
このような感覚は、モチベーションの低下や仕事への興味喪失、さらには職場での不満やストレスの原因となりえます。自分のキャリアの道筋や将来像が見えにくい、または現在の仕事が自身の目指す方向と合致していないと感じたときは、一度立ち止まり、自分のキャリアゴールや価値観を再確認することが大切です。
そして、それに基づいて現在の仕事や環境を再評価し、必要に応じたキャリアの方向性の再検討が求められます。
理由(6)プライベート時間の不足
管理職としての立場は、多くの場合、組織内での業務遂行や部下の指導、プロジェクトの進行監督など、多岐にわたる責任を持つものです。これらの責任を果たすため、日々の業務量は非常に多く、一般的には繁忙なスケジュールが続いていきます。結果として、連休を取る、長期の休暇を計画するなどが難しくなることがよくあります。
さらに、緊急の業務や突発的な問題が発生した場合、管理職としての責任から、休日であっても対応が必要となり、予定していた休暇をキャンセルすることも考えられます。これによって、家族や友人との約束を破る、予定していた趣味の時間を削るなど、プライベートの時間が圧迫されることが増えてきます。
このような状況が長期間続くと、ワークライフバランスが崩れてしまいます。ワークライフバランスとは、仕事と私生活の調和を意味し、このバランスが取れていることは、心身の健康や生活の質を維持する上では非常に重要です。しかし、管理職の負担によりバランスが崩れると、身体的・精神的な疲労が溜まりやすく、仕事の効率や成果にも影響を及ぼすことが考えられます。
さらに、家族や友人との関係にもストレスが生じ、全体的な生活の質が低下する可能性があります。従って、管理職としての責任や業務量と、プライベートの充実との間における適切なバランスが大切です。ゆえに、そのための対策やサポートが必要となることが多いのです。
理由(7)社内の人間関係
職場における人間関係は、私たちの仕事生活において非常に重要な要素となります。毎日のように共に業務を遂行する上司や同僚、部下との関係性は、働く上でのモチベーションや仕事の効率、さらには職場の雰囲気や文化を大きく左右します。そのため、職場の人々との関係にストレスを感じることは、職場における心の負担となり得ます。
特に、上司とのコミュニケーションがうまくいかない、同僚との意見や価値観の衝突、部下との指導方法に関する誤解など、さまざまな原因で人間関係のトラブルが生じることがあります。これらのトラブルは、単なる人間関係の問題を超えて、仕事のパフォーマンスにも直接的な影響を及ぼす可能性があります。
例えば、上司や同僚とのコミュニケーションがスムーズにいかないと、業務上の誤解や情報の伝達ミスが生じるリスクが高まります。部下との関係がこじれると、指導や業務の進行に支障が出やすくなるのです。
さらに、人間関係のトラブルは心理的なストレスを引き起こし、結果として、疲労や焦燥感、不安などのネガティブな感情が増加してしまいがちです。これにより、仕事への意欲の低下やモチベーションの喪失、集中力の欠如といった形で、仕事の質や効率に悪影響を及ぼすことがあります。
このように、人間関係のストレスやトラブルは、職場での心の安定や仕事のパフォーマンスに密接に関連しており、その解決や改善が急募される課題となることが多いです。従って、定期的なコミュニケーションの場の確保や、トラブルを未然に防ぐための研修や教育が重要となります。
理由(8)会社方針に同意できない
職場において、会社の方向性や経営方針は、働くすべての従業員にとって大きな指針となります。これは、まるで航海する船のコンパスのようなもので、会社全体がどのような方向を目指し、どのような価値やビジョンを共有しているのかを示しています。
したがって、この方向性や経営方針に納得がいかないと、毎日の業務の中でのモチベーションの源や、職場における自身の役割や意義を見失うリスクが高まります。
人は、自分の持つ価値観や信念に基づいて行動する生き物です。自分の信じる方向と会社の方向性が一致しているとき、働くことに対する情熱や達成感を感じやすく、その結果、高いパフォーマンスを発揮することができます。しかし、その逆の場合、つまり自分の価値観や信念と会社の経営方針が大きく乖離していると感じると、疑問や不満を抱くことは自然な反応と言えるでしょう。
例えば、自分が持続可能な環境への配慮を重視しているのに、会社が環境問題に対して無関心な経営方針を採るような場合、そのギャップから仕事へのモチベーションが低下する可能性が高まります。また、自分がチームワークや協力を大切に思っているのに、会社が競争を奨励する経営方針をとる場合も、職場での不満や疑問の増大に繋がるでしょう。
このように、自分の価値観と会社の経営方針との間に大きな隔たりが生じると、その中での業務遂行が難しく感じることは少なくありません。そのため、自身の価値観や信念を明確にし、それを基にした求職活動が、長期的な職場での満足度や成果を上げるための重要なステップとなるでしょう。
理由(9)スキルが活かせない状況
人は、自分がこれまで積み上げてきたスキルや経験を持っており、それらを仕事の場で最大限に発揮したいという自然な欲求を持っています。これは、プロフェッショナルとしての誇りや、自分自身の価値を高めるための熱意からくるものでしょう。
しかし、現在の職場や業務内容が、そのスキルや経験を十分に活かせていないと感じると、まるで大きな湖に住む魚が小さな水たまりに閉じ込められているような状態に陥ります。その魚は、本来ならば湖全体を自由に泳ぎ回れるのに、小さな水たまりの中ではその能力を十分に発揮できません。
同様に、自分の持っているスキルや経験を活かせない環境では、自身の可能性や成長を制限されてしまうと感じることがあります。
そして、プロフェッショナルとしてのキャリアを積んでいく上で、自分の能力や経験を最大限に活かせる環境での仕事は、非常に望ましいとされます。なぜなら、それによって自身の成長やキャリアアップの促進ができるからです。
自分のスキルや経験を存分に活かすことができる環境は、新しい課題や問題解決の機会が増え、それによって更なるスキルや経験を積むことができるのです。
管理職・幹部が突然辞めてしまう会社・社長の特徴

企業における管理職や幹部の流動性は、経営側にとって重要な課題の一つです。突如として幹部が退職すると、企業の経営やプロジェクトの進行に深刻な影響を及ぼす場合があります。
続いては管理職・幹部が辞めやすい会社や社長の特徴を解説します。
コミュニケーションが不足している
管理職や幹部としてのポジションは、企業の重要な役割を果たす立場であり、経営陣や上層部とのスムーズなコミュ二ケーションが、日々の業務を円滑に進めるための鍵となります。しかし、実際には多くの管理職や幹部が、このコミュニケーションの不足を感じており、それが退職を考える大きな要因の一つとなっています。
例えば、企業の戦略や方針、ビジョンについての情報が十分に共有されていないと、管理職や幹部はその方向性の正確な把握ができず、結果として現場の実情やニーズと経営陣の思考が乖離するリスクが高まります。
このようなギャップが生じることで、実務を担当する管理職や幹部は混乱や不安を感じやすくなり、それが結果として業績の低下やミスの原因となる可能性もあります。
さらに、管理職や幹部からの意見やフィードバックが経営陣や上層部に伝わりにくい、または十分に受け入れられていないと感じる環境では、彼らのやる気やモチベーションの大きな低下に繋がるのです。
自身の声が反映されないと感じることで、経営陣との信頼関係が損なわれ、長期的には組織全体の活力やイノベーションの源泉が失われることも考えられます。
責任を幹部に押し付ける
経営者や上層部と幹部との関係は、会社の経営をスムーズに進める上で非常に重要なものです。この関係性は、互いの信頼関係に基づいて築かれるもので、この信頼関係が崩れると、会社全体の運営に大きな影響を及ぼすことが考えられます。特に、困難な状況や失敗が発生した際の対応が、この信頼関係を試す大きな要因となります。
幹部は、会社の業績やプロジェクトの進行など、多岐にわたる責任を持っており、その役職ゆえに、高いリスクを背負うことも多いです。そのため、新しい取り組みや挑戦を行う際には、失敗する可能性もあることを理解しています。このような状況で、経営者や上層部からのサポートやバックアップがあると、幹部は安心して挑戦を続けられます。
しかし、困難な状況や失敗が発生した際に、経営者や上層部がその責任を一方的に幹部に押し付けると、これまで築いてきた信頼関係が崩れる恐れがあります。
幹部が常に失敗を恐れる環境に置かれると、新しい取り組みや挑戦を避けるようになり、結果として会社全体の成長や進化が停滞していくでしょう。さらに、長期的には、このような環境は持続しづらく、幹部自身もそのポジションに留まることを避けるようになる可能性が高まります。
評価や報酬が不適切
管理職や幹部は、一般の社員と比べて、会社の業績や組織の方向性に大きな影響を与えるポジションにあります。そのため、彼らの業績や努力の程度は、組織全体の成功に直結すると言っても過言ではありません。しかし、これらの努力や業績が適切に評価されない場合、自分の仕事に対する価値認識や自己評価が低下することが考えられます。
また、給与や報酬は、一人ひとりの業績や努力の評価を具体的に示すものとして、多くの人々にとって非常に重要な要素となります。そのため、自分の努力や業績が正当に評価されない、またはその実績や市場価値に見合った報酬が得られない場合、自分の仕事に対する評価が低いと感じ、不満や不信感を抱きやすくなります。
特に、管理職や幹部が組織の成果や成功に大きく貢献しているのに、その努力や実績が評価や報酬に適切に反映されない状況は、彼らの仕事へのモチベーションの低下を招く原因となりえるのです。
長期的には、このような不満や不信感は、組織全体の業績や士気の低下につながる恐れがあり、組織としての持続的な成長や発展を阻害する要因となりかねません。
従って、管理職や幹部の業績や努力を適切に評価し、その評価を報酬に反映させることは、組織の健全な発展のために非常に重要な評価制度と言えるでしょう。
管理職が辞めたい・辛いと感じているときの対処法

管理職が役職に対しての不安やストレスを感じることは、企業全体の生産性や雰囲気に悪影響を及ぼす可能性があります。このような管理職の不満や悩みを解消するための対処法について、以下に詳しく紹介します。
ヒアリング・面談を実施する
管理職というのは、会社の中でも特に重要な役割を果たしているポジションです。彼らが抱える悩みやストレス、不満は、組織全体の働き手としてのモチベーションや業績に影響を及ぼす可能性があります。
そうした背景を考慮すると、彼らが「辞めたい」とか「辛い」と感じる原因の把握は、組織全体の健全な運営のためにも極めて重要です。
そのための最も効果的な方法は、直接彼らとの対話を通じて情報を得ることです。人は自分の本心や悩みを、ただのアンケートや質問紙よりも、直接の会話を通じて語りやすいものです。また、直接話を聞くことで、紙や画面上の文字だけでは伝わりにくいニュアンスや感情も感じ取れます。
定期的なヒアリングや面談も、管理職の日常の業務やその中での悩み、困難な点などの把握ができるようになります。これによって、彼らの現在の状況や思いを正確に理解することができ、その上で具体的な改善策を考えられるようになります。
また、このような対話の機会を持つこと自体が、管理職にとっての支援や理解があると感じるきっかけとなり、モチベーションの向上にも繋がるでしょう。結果として、組織全体の働き手としての質や業績を高めるための大切なステップとなります。
コミュニケーションを増やす
管理職という立場は、組織内のさまざまな部署や職階、そして経営陣との連携を必要とする非常に要求の多い役職です。このような状況の中で、管理職が感じる不満やストレスの原因として、経営陣や他の部署とのコミュニケーションの不足が指摘されることが非常に多いのです。
コミュニケーションが不足すると、情報の非対称性や誤解が生まれるリスクが高まります。たとえば、経営陣が意図している方針や目標、期待する成果が明確に伝わっていないと、管理職は部下に対して的確な指示やアドバイスができなくなってしまいます。
また、他の部署との情報の共有が不十分な場合、業務の重複や無駄な労力の発生も考えなければいけません。
これを解決するための有効な方法の一つとして、定期的なミーティングや情報共有の場を設けることが挙げられます。これにより、経営陣の意向や目標、他部署の動向などの情報をリアルタイムで把握でき、情報の非対称性や誤解を大きく減少させることが期待できます。
また、これらのコミュニケーションの場を持つことで、管理職自体が経営陣や他部署と直接意見交換を行うことも可能となり、その結果として組織全体の連携や一体感が向上する可能性も高まります。結果的に、管理職の職務の質や組織全体の生産性向上への貢献ができるでしょう。
労働環境を向上させる
過度な労働時間や不適切な労働環境は、多くの職場において管理職のストレスを増加させる大きな要因です。特に、管理職は部下の指導や業績の達成、さらには経営陣との連携など、多岐にわたる業務を担当しているため、その負担が増大することでストレスも相応に増加する傾向があります。
このような状況の中で、過度な労働時間が続くと、管理職自身の健康が損なわれるリスクが高まります。さらに、長時間労働が続くことでプライベートな時間が減少し、家族や趣味といった自分の時間を楽しむ機会が失われることも考えられます。
また、不適切な労働環境とは、物理的な環境だけでなく、十分な情報共有、周囲からの協力が得られていない状況を指すこともあります。これらの条件下では、管理職はより高いパフォーマンスを求められる一方で、それを実現するための必要なサポートが得られないというストレスを大きく感じやすいものです。
このような背景を考慮すると、組織や会社は、管理職のストレスを軽減するための取り組みを積極的に行うべきです。具体的には、労働時間の調整を行い、長時間労働を繰り返さないようなシステムの構築や、適切なリソースや情報の提供、さらには労働環境の全体的な改善などの措置を進めていくことが求められます。
これらの取り組みによって、管理職のストレスを減少させ、より高い業績を達成するための環境を整えられるでしょう。
リーダー研修制度を充実させる
管理職としてのポジションは、単に業務の遂行だけではなく、チームや部署のリーダーシップを取る役割も持っています。このため、役職に就く人々は、業務知識だけでなく、人間関係の構築やリーダーシップに関するスキルも求められることが多いです。
しかし、多くの人が自然にこれらのスキルを持っているわけではなく、研修やトレーニングを通じてこれらのスキルを習得することが一般的です。
管理職としての役割や責任、リーダーシップに関する研修は、管理職の方々が自身の役割やビジョンをより明確に認識し、それに基づいて行動する手助けとなります。例えば、研修を通じて、自分の役割が何であるか、どのように部下やチームを導いていくべきか、どのように効果的なコミュニケーションをとるべきかなどの具体的な知識やスキルを学べます。
さらに、研修の場は、同じような立場の人々が集まる場でもあります。このような環境では、他の管理職の方々との交流の機会が増え、お互いの悩みや課題の共有ができます。このような情報交換は、自身の悩みや課題に対する新しい視点や解決策を得る絶好の機会となり得ます。
他の管理職の方々とのコミュニケーションを通じて、自分だけでは気づかなかった視点を得ることができるだけでなく、共通の課題や悩みに対する解決策を共有することで、より効果的な対応方法を見つけ出せるかもしれません。
このように、管理職研修は、単にスキルや知識を学ぶ場であるだけでなく、同じ立場の仲間とのネットワーキングの場としても非常に有効です。そして、これらの研修を充実させることで、管理職の方々がより自信を持って役割を果たす手助けとなります。
適切な評価制度を構築する
管理職の役割は企業内で非常に重要であり、彼らの業績や成果が組織全体の成功に大きく寄与します。そのため、彼らの業績や成果を適切に評価し、それを報酬や昇進の基準として反映させることは、組織内での公平感やモチベーションの向上に繋がります。
具体的には、管理職が日々の業務を行う上で、自分の努力や成果が正当に評価されると感じることで、より一層の業績向上や新しい取り組みに挑戦する意欲が湧きやすいモノです。逆に、努力が評価されない、または不適切に評価されると感じると、モチベーションの低下や業績の停滞、さらには退職を考える原因となることもあります。
さらに、評価制度に透明性を持たせることで、管理職はどのような基準や指標に基づいた評価に対する明確な理解がしやすくなります。これにより、自分がどのような業績や成果を上げれば報酬や昇進のチャンスが得られるのか、また現在の自身の位置がどこにあるのかの具体的な認知が可能です。
このような透明性がある評価制度は、管理職の不安や不満を軽減するだけでなく、組織全体の成長や発展にも寄与する要因となるでしょう。
幹部が辞める会社の未来は明るくない?

経営幹部が辞めていなくても、経営者と意見がかみ合わなくなってくると従業員への影響が出てきます。
会社として大事にしたいコアバリュー(価値観)がしっかり決まっているのであれば、その対策として幹部がコアバリューを共有してくれているのかは確認する必要があります。もし、そのコアバリューを共有できていなかったとしたら、その幹部社員は辞めて当然ですし、会社として長期的に見ると辞めてくれてよかったとポジティブに捉えることができます。
幹部自身はコアバリューを大事にしてくれていないのに、その幹部がいてくれないと困るということで、経営者がすごく気をつかっていたり、いびつな対応をしていたりするケースは実際よくあります。
しかし、コアバリューが共有できていなければ、早かれ遅かれ幹部社員の離職は起きるものです。幹部が辞めていく状態というのはあまり気持ちの良い状態ではありませんが、将来的に起きるのであれば今起きて良かったと思って良いでしょう。
経営者と幹部との相違があるのはよくあることです。しかし、経営者は社員に辞められると実働が困ることになるので、辞めさせたくないがために一歩引いて対応しているケースがあります。それを幹部が利用してさらに要求を通すようになるのです。
バリューを共有できておらず、また仕事も出来ないのであれば辞めさせることに悩みはないかもしれませんが、幹部は仕事ができることが多いので、なかなかそういった状態であっても辞めさせられないのが現状です。
しかし、社内でその幹部の味方となる社員がでてくると、結果的に会社が2分化してしまい、最終的に経営者とケンカ別れのような形で独立されてしまうケースもあります。会社が大きくなればなるほどダメージが大きいので早いうちに幹部とコアバリューを確認した方が良いでしょう。
なんとなく幹部と合わないと思っている場合では、コアバリューを言語化できていないことが多いです。
コアバリューとは、会社にとって不可欠で不変の指針となる理念や原理のことです。コアバリューは会社が独自に決めるものですが、数としては3〜7つくらいに止めることを推奨しています。
コアバリューが言語化されていたら、会社として大事にするコアバリューのなかで、相手のどの部分が当てはまっていないのか、当てはまっていないのであれば改善を要求する、もしくは納得できないのであれば会社を去ってもらうなどの対処ができるようになります。
では、コアバリューを言語化するためにはどうしたらいいのでしょうか?
「ビジョナリー・カンパニー2」という有名なビジネス書の第3章に「偉大な企業への飛躍をもたらした経営者は、はじめにバスの目的地を決め、次に旅を共にする人々を乗せる方法を取ったのではない。はじめに適切な人をバスに乗せ、不適切な人を降ろし、その後にどこに向かうかを決めている。」という文があります。
人材採用を「バスに乗せる」と表現しているのです。つまり、この人たちとバスに乗りたいという正しい人(コアバリューを共有している人)を決めてから、次に目的地を決めることが大切なのです。
まとめ

管理職が退職を考える背景には、激務、仕事のストレス、部下の管理の難しさ、給与の不足、キャリアの不安、プライベートの時間不足、社内の人間関係の問題、会社の方針への不同意、そして自身のスキルが活かせないといった多くの理由があります。これらの理由は、管理職のモチベーションを低下させる要因となっています。
多くの経営者やHR担当者が頭を悩ませているのが、「幹部や管理職の退職」の問題です。これは単なる人事の問題を超え、組織の基盤そのものが揺らぐ可能性があるため、非常にデリケートな課題となっています。
しかし、なぜ幹部が辞めるのでしょうか?
その背後には、会社の方針の不明瞭さやコミュニケーションの不足、報酬や評価の不公平感など、様々な要因が絡んでいます。
このような組織の課題を解決するための手法として、EOS(Entrepreneurial Operating System)があります。EOSは、企業の様々な課題を解消するための経営フレームワークを提供しています。
まず、EOSはビジョンの明確化をサポートします。これにより、会社全体で共有すべき方針や目標がはっきりとし、全員が同じ方向を向いて動くことが可能です。幹部や管理職も、自らの役割や目標を明確に理解し、自身の業績を会社のビジョン達成に貢献するものとして捉えることができます。
次に、EOSはコミュニケーションの流れを最適化します。日々の業務の中での意見やフィードバックが上層部へスムーズに伝わるようになると、幹部の不安や疑問が早期に解消されるため、彼らの退職を防ぐ手助けとなります。
さらに、EOSを採用することで、公平かつ透明性のある評価制度の構築が可能です。これによって、幹部の業績や貢献が適切に評価され、それに見合った報酬や昇進のチャンスが得られるようになります。
幹部や管理職の退職は企業にとって深刻な問題ですが、その原因を根本から解消するための手法としてEOSを検討してみてはいかがでしょうか。幹部たちのモチベーションを維持し、彼らの力を最大限に引き出すためのサポートを、EOSが提供します。
幹部の退職問題に頭を悩ませている経営者の皆さん、ぜひEOS®の知見が詰まっているトラクションの第一章を無料ダウンロードできるので、まずはこちらのトラクションをぜひお読みください。



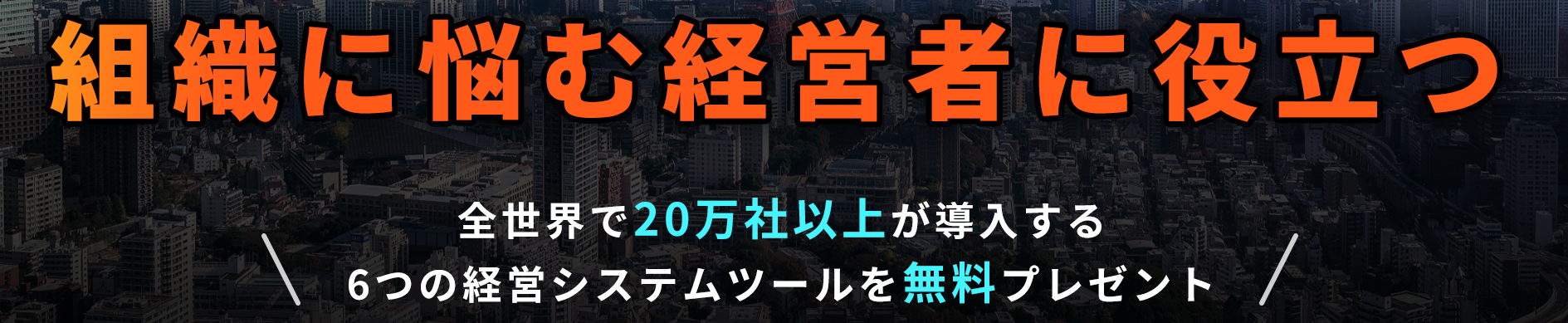
コメント